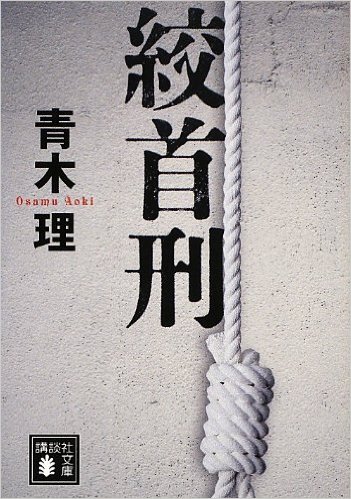
死刑という刑罰に直接関わらざるを得なかった人々~死刑囚、被害者遺族、刑務官、宗教教誨師、弁護人等々~に直接話を聞き、それに基づいて書かれた本書は、死刑制度に賛成・反対ということではなく、死刑制度の是非を考える前提としての事実を提示したいという意図で書かれたものである。
それゆえ、死刑制度に賛成とか反対とかいう主張は述べられてない。
むしろ、著者の主張は抑えられ、死刑判決が出されるに至った事件の悲惨さ残酷さとともに、死刑囚の過酷な成育歴を述べ、そしてまた事件の重大さに戻る。
死刑執行の光景、飯塚事件を題材とする冤罪問題も採り上げているが、一番描かれているのは、直接取材して話を聞いた人たちの思い~時間とともに変化したり揺らいだり、相反するように見える思いが併存したり、その時々の感情と「あるべきもの」とに引き裂かれたり、それでもやはり消えない思いに踏みとどまったり、刻々と揺れ動いている生身の人間の心の一断面である。
それは、決して単純で「わかりやすい」ものではなく、他者の憶測で想定できるものではない、複雑で「わかりにくい」ものである。
でも、わかりにくく、論理的でないのが、人間という存在だと思う。
とりわけ、犯罪被害者遺族の言葉には胸が詰まる。
「赦せない」ことの悲痛と、苦悩と、逃れられないその重さ。
他方で、「死刑判決で死をもって償えというのは、反省する必要ないから死ねということ」だから「全く反省していない」と言い捨ててしまう一人の死刑囚の言葉に、その言葉の向こうにあるものを考えあぐねてしまう。
そんな「わかりにくい」人間をわかりにくいまま提示している本書は、死刑制度が今もあるこの国で、遠くから抽象的に想像するのではなく、現に関わらざるを得なかった人の思いをじかに感じた上で死刑について考えるために、是非手にとっていただきたい1冊である。
(会員 大杉光子)
「終身刑を考える」 大阪弁護士会死刑廃止検討プロジェクトチーム 2014年 日本経論社
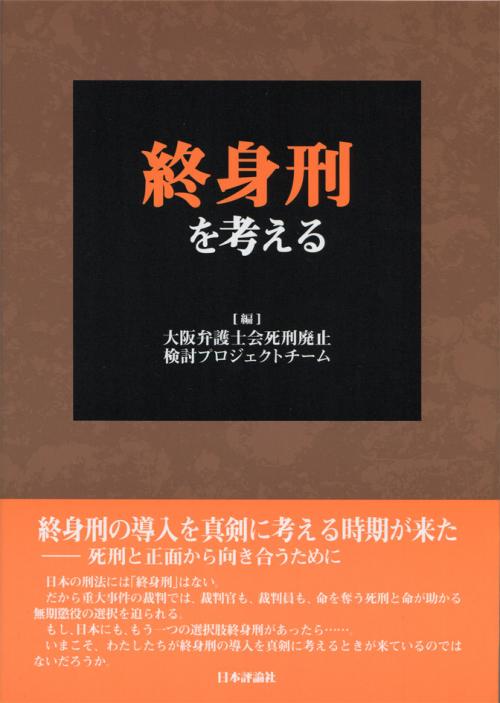
本書 は、2013年3月16日に大阪弁護士会で開催されたシンポジウム「死刑と無期刑の間~終身刑の導入と死刑廃止について考える」をまとめて、加筆された本である。
シンポジウムのパネリストは、死刑制度を考える上でそうそうたる気鋭のメンバーばかりであり、そのメンバーの発言や考えを一冊の本でまとめて、しかも、手軽に読めるという点で、極めて有用な本である。
浜井浩一教授(龍谷大学法科大学院)による凶悪事件の動向とその背景では、客観的なデータをもとに凶悪犯罪が減少していること、それにもかかわらず体感治安が悪化している理由、他方で窃盗などで受刑する高齢者が増えるという異常な状況が発生し、刑務所に社会的弱者が集まっていること、無期刑が終身刑化していること、死刑の犯罪抑止力、死刑に関する世論調査結果に対する評価が、極めて冷静に整理されている。
石塚伸一教授(龍谷大学法科大学院)のパートでは、絞首刑が残虐な刑罰なのかが残虐性をめぐる歴史と最新の知見が紹介され、世界における死刑と終身刑の状況が紹介されています。石塚教授は、かつては、死刑と終身刑化した無期刑の両方を同時に廃止すべきとの立場で全面戦争を挑んでいたけれども、それでは勝ち目がない、現実は動かないと考えるに至り、終身刑の導入を議論の俎上に載せるべきと述べられる。
布施勇如龍谷大学矯正・保護総合センター嘱託研究員からは、アメリカのテキサス州の実情が報告されます。テキサス州は死刑存置州で、アメリカでもっとも多くの死刑を執行している州ですが、そのテキサス州でも近年は死刑判決、執行が激減していることが報告されている。
永田憲史准教授〔関西大学)からは、永山判決の死刑選択基準と光市母子殺害事件の最高裁判決がどのような関係にあるのか、裁判員制度後の死刑選択基準がどのようになっているのかについて、詳細な分析がわかりやすく説明されている。
安田好弘弁護士、後藤貞人弁護士という刑事事件の第一人者からも、弁護実践、そして生身の人間である被告人と直接無期かった経験から、死刑を廃止するために終身刑を導入すべきであるとの意見が述べられる。
死刑廃止と終身刑の関係については、終身刑は一生刑務所から出ることができないという絶望的な状況の下で自然死するまで行かされるのであり死刑以上に残虐であるとか、将来に希望のない受刑者の処遇に困難を極めるとか、無期刑の上に刑罰を設けることで厳罰化が進むという理由で、終身刑そのものに反対する意見がある。
死刑廃止のために終身刑の導入に賛成する立場も、死刑の代替刑として終身刑を導入すべきという見解と、死刑を存置したままでもまず終身刑を導入すべきという見解がある。
死刑廃止という立場を共通にしていても、終身刑については、さまざまに意見が分かれ対立してきた。
その対立が、死刑廃止を困難にし、議論を前に進めることができない原因となってきたことは否めない。
本書で展開されている議論は、そうした議論に終止符を打ち、死刑廃止を現実的に前に進めようとする戦略的な議論である。
(副代表 辻 孝司)
「死刑執行人サンソン」-国王ルイ十六世の首を刎ねた男 安達正勝 2003年 集英社新書

かつて、フランスでは、死刑執行人の職は特定の家系によって世襲されていた。
その家系を継ぐものは、その職務遂行に深い苦悩を覚えていたが、その職を自らの意思で離れることは事実上許されなかった。
彼らは、不浄の存在とされ、徹底した嫌悪と差別の対象だった。
本書は、パリの死刑執行人の職を世襲したサンソン家の四代目当主・シャルル-アンリ・サンソンの人生を中心に描かれる。
彼は、敬虔なキリスト教徒として、人の命を奪う仕事に苦悩する一方、国王の委任により、裁判所の命じた判決を執行する自らの職が恥辱の存在とされることに対しては敢然と反論する。
しかし、時代の巡りあわせにより、彼は自分の仕事の正当性の拠り所であった国王を、革命の熱狂の中で、自ら処刑しなければならなくなり、混乱と苦悩は頂点に達した。
彼はその後も、革命政府の下で、さらにナポレオン帝政の下で、二千数百人を処刑し続け、そして死刑制度の廃止を願い続けた。
死刑執行人は、命令に従って忠実に職務を実行する存在であり、彼の意思によって人の命を奪う存在ではない。
死刑を要請するのは、国家・社会の側である。
それどころか、国家・社会は公開処刑という形で、死刑執行を「消費」さえしてきた。
ところが、死刑執行という苛烈な職務から生じる苦悩だけは、執行人が一身に受け、これを命じた国家・社会の側は、彼の苦悩をあたかも他人事のように扱い、彼を「人殺しの職」として嫌悪し、差別さえした。
この構造は、古今東西の死刑制度に普遍的なものであることを、本書は教える。
公開処刑が密行的な処刑に変わろうとも、社会が死刑を要請し、「消費」する構造は変わらない(むしろ、現代社会では、マスコミを通じてその構造は拡大しているとも言い得る)。
死刑執行の任にあたる刑務官の重圧に目が向けられることがあっても、それは「彼の」苦悩として語られる。
しかし、死刑執行に携わる者の苦悩は、本来ならばこれを命じる責任者が負うべき苦悩である。
その責任者は、絶対王政下であれば国王であった。
近代民主主義社会においては、主権者たる国民ということになるだろう。
その主権者国民が、死刑制度とその執行から生じる苦悩を、我が身の責任として受け止めるという感覚から免れている。
その責任感覚の薄さは、絶対王政における国王の立場と変わらない。
あるいは、代表民主制という大掛かりな装置の影で、現代社会に生きる我々は、かつての国王よりもはるかに気が軽い「免責の錯覚」に身を委ねているのかもしれない。
本書は、「フランス革命の裏面史」(本書カバー裏面解説)としても、数奇な運命をたどった個人の伝記的な物語としても読むことも可能であるが、是非、死刑制度を考えるときに、主人公サンソンの苦悩を「彼の苦悩」として知るのではなく、読者自らの問題として悩むことができるか、という視点で読んでいただきたい本である。
(会員 石側亮太)

本書は、死刑制度の是非や死刑存廃論議を直接取り上げるものではない(本書16頁)。
これまでの日本の裁判で、いかなる場合に死刑が選択され、いかなる場合に死刑が回避されてきたか、言い換えれば日本の死刑制度が法廷で実現しようとしてきた「正義」とは何であったのかを分析しようと試みるのが本書である。
「問われているのは、人命の価値ではない。死刑判断は、人命という価値だけでは考えられない。
死刑が問題になるのは殺人事件であり、そうである以上、どの事件の加害者も被害者の命を奪っている。
人命は最高の価値であるとしても、それだけでは死刑判断にはいたらないのである。では、
人命の価値以外のどのような価値が加わったときに、死刑かそうでないかが分かれるのか。本書は、それを開示する書である」(本書「まえがき」)。
著者は、「永山基準」を「基準」とは呼べないとして批判する。
ただ、永山基準そのものの当否を論じるものではない。
永山基準は、死刑判断の考慮要素を列挙して「あらゆる要素を考慮してやむを得ない場合にのみ死刑が適用される」というものであるが、それだけでは、いかなる場合に「やむを得ない」と言えるのか、分析の視点としても判断の基準としても不十分である、つまり「永山基準だけでは分からない」という意味での批判である。
著者は、死刑が問題となる事件を「死刑空間1~5」と名付ける5つの基本類型(「市民生活と極限的犯罪被害」「大量殺人と社会防衛」「永劫回帰する犯罪性向」「閉じられた空間の重罪」「金銭目的と犯行計画性の秩序」)と、「死刑空間A~D」と名付ける4つの修正要素(「被告人の恵まれない境遇」「心の問題、心の闇と死刑」「少年という免罪符」「死刑の功利主義」)に分類し、それぞれの「空間」ごとに、そこで作用する価値観、「正義」や「善」「悪」の考え方などを分析してゆく。「死刑空間」という耳慣れない用語を使うのは、それぞれの「空間」ごとに、死刑判断における「正義」の要素(一般的な裁判用語では「情状」だろう)の作用の仕方が違い、一元的な分析では解明できないと考えているからだろう。
著者は元裁判官であり、かつてある事件の第一審死刑判決に主任裁判官として関与したことを明らかにしている(当該事件は控訴審で無期懲役になった)が、死刑存廃論についての自らの立場はあえて明らかにせず、古今の社会・政治思想や哲学などの知見を参照しながら、極めて抑制的・中立的な筆致で論を進めているのが本書の特徴であり、いかなる立場からも参考になる。
ややもすると「論じ尽くされた」観のある死刑制度(存廃)論に、新たな議論の観点を提供する一冊である。 (会員 石側亮太)
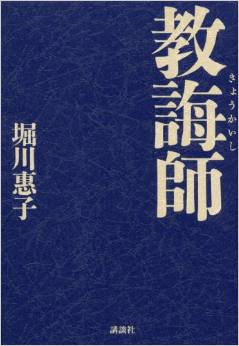
本書は、14歳の夏にヒロシマで被爆した教誨師渡邉普相から、作者に託された遺言である。
死刑確定囚は希望すれば宗教家による教誨を受けることができる。
しかし、その教誨でどのようなことが行われているのか、死刑確定囚がどのような話をしたのかは秘密であり、具体的な内容が教誨室の外に出ることはない。
教誨師は死刑の執行に立ち会う。しかし、誰がどのように執行されていったのかは秘密であり、執行の様子が執行室の外に出ることはない。
渡邉はその死後にのみ公にすること条件にその秘密を作者に告白する。死刑確定囚の様子、死刑執行の様子が具体的に生々しく語られる。
渡邉は、若くして教誨師となり、死刑により命を奪うことを宣告された人々と向き合う。
浄土真宗の教え「悪人正機」の教えを伝えることで、死刑を執行される人々に「救い」を与えようとする。
しかし、渡邊は自らの職務に懊悩し、やがてアルコールに溺れ、アル中で入院まですることとなる。
その事実を死刑確定囚たちにさらけ出して初めて渡邉は気付く、自分の教誨は一方通行だった、大上段に構え、何かを伝えなくてはと焦ってばかりいたと、
教義を教え込むことよりも、ほんのひと時でもほっと出る時間、考えることのできる「空間」を作ることこそが大切なのだと。
事実を知らなければ、私たちは死刑について意見を持つことなどできない。
本書を通じて伝えられた事実は、死刑の問題を考える上で極めて重要である。
死刑確定囚のこと、死刑執行のこと、執行する人たちのこと、ぜひ、本書を読んで知っていただきたい。
渡邊の告白をまとめ上げた作者の筆力にも感嘆せざるを得ない。 (副代表 辻 孝司)

韓国で多くの文学賞を受賞しているベストセラー女流作家コン・ジヨンの同名小説の映画化。
韓国での観客動員は300万人!
公開時に韓国歴代恋愛映画観客動員数ナンバーワンを記録したそうです。
元歌手ユジョンは3度の自殺をしますが、失敗して死にきることはできません。
死刑囚との面会をしている叔母シスターモニカに誘われて、何となく刑務所に行き、そこで三人の女性を殺して死刑囚になったユンスと知り合います。
初めはユンスに怯え、近寄ろうとしなかったユジョンですが、叔母の代わりに面会に行くなどしているうちに、いつの間にか毎週木曜に面会することになります。
一日も早い死刑執行を望むユンスに、ユジョンは自分に似たものを感じ、ユンスもまた、棘のある言葉ばかりを投げつけるユジョンに、自分に似たものを感 じていきます。
裕福な家で育ったユジョンと孤児のユンス。全く違う人生を送って来た二人でしたが、面会を繰り返すうちに互いを思いやるようになり、お互いに誰にも言えなかった過去を告白します。
やがて二人は、心の奥に秘 めていた深い傷を癒しあえるかけがえのない存在となります。
しかし、ある日、突然に刑は執行されます。
執行されるユンスを見送るユジョン。
人に言えない悲しい過去を持ち、生きる望みを失っていた二人が出会い、つかの間の幸せな時間を過ごす様を、繊細に描かれています。
被害者遺族の複雑な心情も丁寧に描かれています。
被害者遺族との面談でユンスも遺族も取り乱してしまいます。
しかし、面談し、直接思いをぶつけることで遺族の心の中に赦しの萌芽も生まれてきます。
死刑囚が収容されている刑務所の様子や、宗教教誨師との面談、死刑執行の様子などもリアルに描かれています。
人が人の命を奪うこと、たとえ法による場合であっても、本当に許されるのか?
命を奪うことの悲しさが伝わる映画です。
映画 「デッドマン・ウォーキング」 ティム・ロビンス監督 1995年
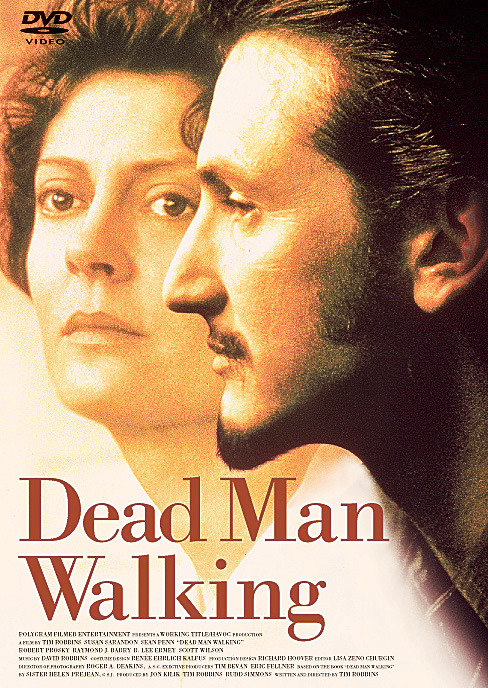
「愛」という価値観。これに対する「目には目を、歯に歯を」という価値観。
本作品には、この両者の価値観が登場する。
マシュー・ポンスレットは、若いカップルに対する殺人・強姦殺人の罪で死刑囚となる。
修道女であるヘレン・プレジャンは、マシューから手紙をもらったことをきっかけとして、死刑が執行されるまでのマシューの精神アドバイザーとなる。
本作品においては、死刑囚の立場、被害者の遺族の立場、死刑囚の家族の立場というそれぞれの立場からの描写がなされているが、ヘレンは、どの立場の者に対しても「愛」をもって接する。
事件に向き合おうともせず、人種差別的な発言をする死刑囚マシュー。
愛する息子・娘を惨殺されて深い悲しみと死刑囚に対する大きな憎しみを抱える被害者の遺族。
事件への対応に戸惑いを見せる死刑囚の家族。
この絶望的な状況においても、人間の可能性を信じて、決して諦めることなく、それぞれの立場の者に「愛」をもって接し、それぞれの距離を少しでも近づけようと努力するヘレンに深い感銘を受けた。
結局、マシューの死刑は執行され、「目には目を、歯に歯を」という価値観が実現されることになるが、最期にマシューが遺した言葉が印象的であった。
「いかなる場合においても、人の命を奪うことは間違っている。それは、国家によってもだ。」
死刑の執行により、死刑囚の家族の深い悲しみという負の連鎖が繰り返されることになる。
被害者の遺族の一人が、マシューの葬儀の場を訪れて、ヘレンにこう述べた。
「それでもまだ犯人に対する憎しみが消えない。」
死刑の執行によっても救われることのない被害者の遺族に対して、ヘレンは、「努力すれば、憎しみは消える。」と語りかけて、やはり「愛」をもって接するのであった。
「死刑の基準~『永山裁判』が遺したもの」 堀川惠子 2009年 日本評論社
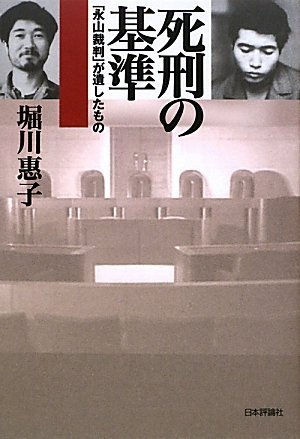
これまで死刑判決が下されるたびに引用されてきたいわゆる「永山基準」。
著者は,光市母子殺害事件を取材していく中で,「永山基準」とはいったい何なのか,「死刑の基準」とは何なのか,徹底的に調べてみようと決心し,永山則夫が遺した手つかずの遺品を読み込み,親族,支援者,裁判に関わった法曹関係者等様々な関係者に取材を重ね,本書を書き上げている。
著者が永山則夫という1人の死刑囚の足跡を辿って行き着いた答えは,「人を処刑する画一的な基準はありえない」という一言に尽きる。
人を裁き,そして殺すという判断を下すのであれば,被告人が辿った人生を徹底的に探るだけでなく,裁く側の心の奥底にある倫理観,死生観,そして生き様までをも厳しく問い直し,剥き出しにする作業となるのであり,そこには基準などありえないと著者は言う。
著者のように永山事件に関して徹底的に取材をしてきた人でも,「人は,人を裁けるのか」という問いに対して明言することに躊躇するという。
裁判員時代を迎え,「人は,人を裁けるのか」は何かという問いは,私たち1人1人の市民に向けられているはずである。
自分たちがそれだけの重い責務を負っているということを自覚するためにも,一読を勧めたい一冊である。
「裁かれた命 ~ 死刑囚から届いた手紙~」 堀川惠子 2011年 講談社

著者は、調査に調査を重ねて、死刑に処せられた長谷川氏とその家族の人生を明らかにしている。
明らかにされた事実は、長谷川氏に対する死刑判決が誤りであったことを雄弁に語っている。
例えば、長谷川氏が控訴審からの弁護人に宛てた手紙。
長谷川氏が自らに死刑を求刑した検察官に宛てた手紙。
これらは、長谷川氏の更生(可能性)の証左である。
検察官は、手紙のやりとりをするうち、長谷川氏に恩赦を受けさせようと上司に相談さえした。
長谷川氏は、死刑判決が下されなければこの境地に至らなかったであろうか。
それは分からない。ただ、長谷川氏に対する死刑の執行は、誤りであったというほかない。
弁護人としてみた場合、この著書は、死刑求刑事案では、被告人の人生をすべて暴き出すことが最善の弁護活動であることを示している。
つまり、弁護人は、被告人の人生を、この著者が行ったレベルまで調査し尽くさなければならない。
長谷川氏については、一審の弁護人がもっと時間をかけて調査を行っていれば、犯情についての分析が深められていれば、死刑判決を回避できた可能性がある。
私が死刑制度の廃止を求める1つの理由がここにある。
不適切・不十分な情状弁護による死刑判決は、再審による救済が受けられない点で、まったく取り返しがつかない。
そして、死刑は「揺れる」。時代によって、裁判所によって、検察官によって、弁護人によって、市民によって。裁かれなくてもよい命が裁かれる可能性がある。
上に述べた検察官は、かの土本武司氏であるが、土本氏の「苦悩」を通じて、人を裁くことの難しさと、その責任の真の意味が突き付けられる。
皆さんに是非お勧めしたい著書である。

著者は、精神科医で、かつ作家でもあるが、この本は、精神科の医務官として東京拘置所に勤務した経験に基づいて書かれている。
死刑が確定したからといって、すぐに刑が執行されるわけではない。
条文上は、判決確定から6ヶ月以内とされているが、何年間も執行されないことも多い。
いつ執行されるのかはわからないが、しかし、確実に殺されるという恐怖に苛まれ、死刑確定者の精神は揺れ動く。
精神に異常を来すことで迫り来る恐怖から逃れようとする者、宗教に救いを求める者、ひたすら生き急ぐ者。
加賀氏は東京拘置所の精神科医として死刑確定者と向き合いつつ、一人の人間としてその精神を見つめている。
また、「濃縮された時間」を生き急ぐ死刑確定者に対して、「薄められた時間」に適応して退行する無期受刑者の話は、終身刑の導入を考える上でも思い致すべきものだろう。
現在では、拘置所の医務官といえども、加賀氏のように気軽に死刑確定者のところに一人で出かけていって話し込むことはできないそうなので、本書は死刑確定者の実情を知る貴重な記録である。
(会員 大杉光子)
「弟を殺した彼と、僕。」 原田正治 2004年 株式会社ポプラ社
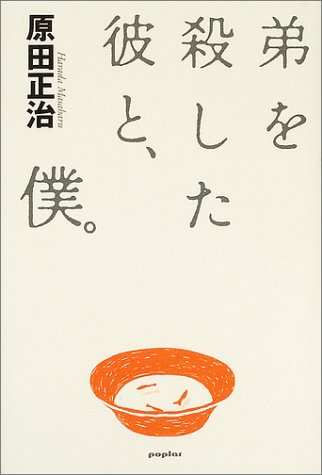
1983年、弟が殺害された。
長谷川君が加害者と判明すると、その死刑を強く望んだ。
しかし、1993年から長谷川君と面会を重ね、長谷川君に対する死刑執行の停止を求めるように。
やがて、その思いは、死刑制度廃止や犯罪被害者と加害者の出会いを考える活動へとつながる。
この本には、そんな原田さんの20年あまりが綴られている。
被害者遺族を型にはめないでほしい。
被害者のため、遺族のため、といって死刑にするのは間違っている。
被害者遺族も加害者も、時間が経過するにつれて変化する。
その変化を断絶する死刑制度には絶対に反対する。
悩み苦しんだ後にたどりついた原田さんの訴えを、ぜひ一読いただきたい。
「ゆれる死刑 アメリカと日本」 小倉孝保 2011年 岩波書店
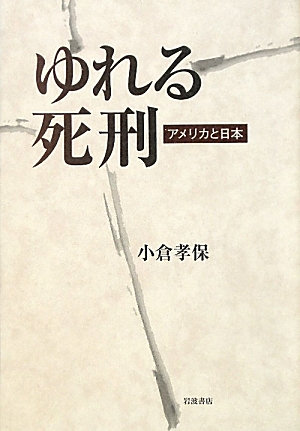
2008年6月17日,日本で宮崎勤死刑囚の死刑が執行された。
この日,新聞記者である著者は,米国オクラホマ州で,ショート死刑囚の死刑執行に立ち会った。
米国ではマスコミ関係者が死刑執行に立ち会うことができる。
著者はマスコミ関係者として執行への立会いが許可されたのであった。
驚くべきことに,著者はこの数日前,ショート死刑囚にインタビューをしている。本書を読めば,米国における死刑の実態がよく分かる。
本書は,新聞記者である著者が日本と米国の両国において死刑囚,被害者遺族,元死刑囚(冤罪で釈放),元検察官等に対して丁寧な取材活動をした記録であると言って良い。
米国では,死刑執行の立会いがマスコミ関係者に許可され,死刑囚へのインタビューも可能である。
だから,丁寧な取材をすれば死刑の実態が明らかになる。
他方,日本では,死刑の情報は全く公開されないから,どれほど丁寧に取材をしても,死刑の実態は見えてこない。
死刑を肯定するにせよ否定するにせよ,何よりもまず,死刑についての情報が公開されることが必要である。この当たり前のことを,本書は再認識させてくれる。
「アメリカで、死刑をみた」 布施勇如 2008年 現代人文社

著者は新聞記者であるが、本書は著者が2002年から2004年までの2年間アメリカのオクラホマ大学に留学した際の死刑制度についての調査・研究の集大成である。
オクラホマ州の1977年から2011年までの死刑執行数は96で、テキサス州、バージニア州に次ぎ(ウィキペディアによる)、地理的にもテキサス州の北に隣接していること、オクラホマ・シティの連邦ビル爆破事件(1995年、死者168名)という大事件のあったこと等から、アメリカにおける死刑制度について多くのことを知ることができる州である。
そこでの著者の調査先は、死刑が確定しながら後に無実とされ、釈放された「死刑囚」、被害者遺族(具体的には、娘を殺害された父親、孫を殺害された祖母、娘を殺害された母)、(アメリカで最も死刑執行の多い)テキサス州の刑務所博物館、同州ハリス郡の元検事正、前記連邦ビル爆破事件により仮釈放なしの終身刑判決を受けた被告人テリー・ニコルズ(主犯のティモシー・マックベイは2001年に死刑が執行された。)の(死刑制度専門)弁護人、アメリカ矯正協会の大会で行われた死刑賛成派と反対派の討論会、オクラホマ刑務所で執行された死刑への立会、カトリックのシスターと死刑囚の心の通い合いを描いた映画「デッドマンウォーキング」のモデルとなったシスター等である。
以上のように、調査先は、死刑制度に対する賛否のみならず(前記の被害者遺族の中にも、死刑制度賛成派と廃止派がある)、死刑制度に対する視点も様々であり(死刑を言い渡される者、執行する者、死刑事件を弁護する者、死刑囚を支援する者等々)、それ故、死刑制度を考える上で基調かつ興味深い情報を提供してくれる著作と言える。
著者は、本書の中で、「死刑の是非についての、私の『答え』はいまだに見つかっていない。」と述べている。
しかし、本書には、前記連邦ビル爆破事件により娘を殺害されたバド氏(当初は主犯のマックベイに対する死刑を望んでいたが、マックベイの父親ビルと会い、「ビルは僕以上の被害者だ。」と思うようになり、死刑制度制度廃止を訴えるようになった。)の「死刑制度の廃止に必要なことは3つある。一に教育、二に教育、三に教育です。多くの人が死刑に関する基本的事実を知らない。」という言葉が引用されている。
又、著者は死刑制度執行に立ち会ったあと、著者も含め死刑執行に立ち会った人全てが、それが州による「殺人」だとは認識せず、その行為に参加しているという実感もやましさも抱かずに済んだという感想を述べている。そして、このことから、死刑執行に立ち会った人のみならず、「知事や議員、検事正を選挙で選んだ州民も含め、誰もが当事者なのに、誰も当事者であることを意識せず、又、その重みと痛みをほとんど感じないまま、わずかに数分でやり遂げられてしまう『極刑』とは、いったい何なのだろうか。」という疑問を投げかけている。
著者の意図にかかわらず、我々は、本書に記載されている様な「死刑に関する基本事実」を知れば知るほど、そして、自らが死刑執行の当事者であることを自覚すればするほど、死刑制度に反対せざるを得ないのである。
